北方領土・択捉島出身の三上洋一さん(87)=神奈川県相模原市在住=は、引き揚げてから80年近くたった今も、故郷・留別(るべつ)村を思い出さない日はない。島について知る人が年々少なくなる中、当時の暮らしぶりや旧ソ連軍の侵攻、2年間のロシア人との共住生活などについて聞いた。(北海道新聞デジタル2024/5/25)
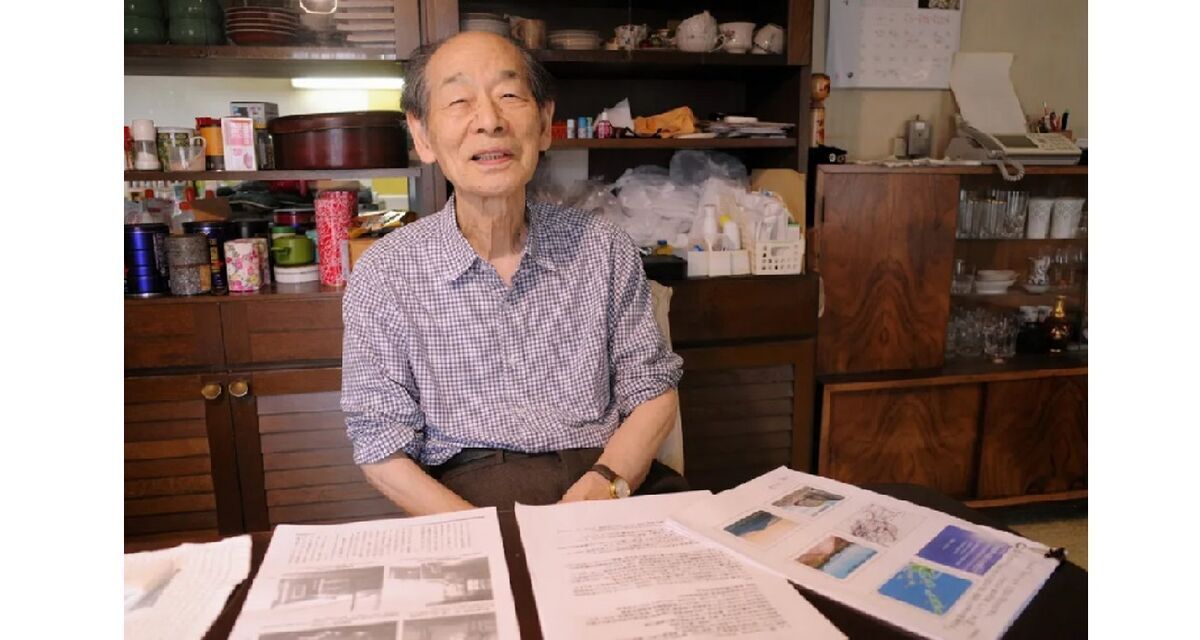
神奈川県相模原市の自宅で「故郷・留別村を毎日思い出す」と語る三上洋一さん=4月30日
■三越から商品取り寄せも
―留別はオホーツク海に面した択捉島中部の村ですね。島の思い出について聞かせてください。
「最初に思い出すのは、風見山です。山のふもとには留別川が流れています。山からは村が一望できました。村はほとんどが平屋で、2階建てはあまりありませんでした。どこの家に誰が住んでいるかは今でも頭に浮かびますね。金銭的には裕福な人が多かったです。商店での買い物は半年に1回のツケ払い。しゃれた商品は三越などから通信販売のような形で取り寄せていました。私はマヨネーズが島に届くのを待ち焦がれていました。船は主に根室や函館から来ていました」
―三上さんの一家が択捉島で暮らすようになった経緯は。
「明治のはじめ、曽祖父は神戸に住み、ラッコやテンなどの毛皮の貿易業を営んでいました。ところが乱獲で入手困難になったため、缶詰の輸出を思いつき、函館に事務所を開きました。祖父はタラバガニの漁業権を択捉島太平洋側に、サケ・マスの漁業権をオホーツク海側に得て、缶詰工場を建てました。また、郵便局の権利を買い、逓送業を始めました。択捉島に定住するようになったのは祖父の代からです。それまで冬は島に留守番を残し、函館で暮らしていました。父は留別郵便局の局長でしたが、家業は漁業、サケ・マスの缶詰業です。サケが燻製(くんせい)工場でぶら下がっているのを覚えています」

2006年8月に約60年ぶりに訪れた留別の風見山から、戦前の様子を説明する三上さん。右に見えるのは留別川
■すり切れるまで聴いたレコード
―島の暮らしや自然はどうでしたか。
「1年の半分は雪の下です。冬をどうやって過ごすかに知恵を絞り、大人たちはよく読書会をやっていました。どこの家もレコードをすり切れるまで聴いていました。ラジオは雪が降ると、ノイズが入り聴けないこともありました。私は春の訪れを楽しみにしていました。6月に桜が咲くと、サクラマスがやってきます。6月中旬にハマナスが咲くと、カラフトマス、8月にコケモモがなると、サケがやってくるんです。そんな風に植物を見ると、なんの魚が来るかわかりました」
―島に戦争の影はありましたか。
「留別尋常小学校に入学した年にアッツ島で日本軍が玉砕しました。小学校1年の時に君が代を習い、2番目がアッツ島で亡くなった兵士をたたえる歌です。3番目が英霊を迎える歌で、島から出征した兵士が亡くなった時に歌いました。また、1945年になるとわが家と郵便局には日本軍の将校が訪れるようになりました。郵便局は軍にとって需要な通信網の一部になっていたのです」
■ソ連軍上陸「思ってもいなかった」
―45年8月に旧ソ連軍が島に上陸しました。
「8月28日、川幅の向こう側が見えないほど、霧が深い日でした。ソ連兵500人が2隻の船に乗り、留別川の右岸と左岸の浜辺に上陸しました。後になって上陸は午前10時ごろだったと知りました。その前の45年の夏にはアメリカ軍の艦砲射撃があり、私たちは山陰に逃げました。まさかソ連軍が上陸してくるとは思ってもいなかったので、留別の住民はひどく驚きました」
「ソ連軍は留別に上陸後、風見山を陣取り、機関銃の砲台を構えました。アンテナを見て、無線局だと気付いたのか、ソ連兵は郵便局に来ました。この日、郵便局では10人の局員のうち7人がいました。ソ連兵は『通信局か』と聞き、ロシア語が少しわかる父がうなずくと、1人を残して他の局員は追い出されたそうです」

三上さんの父が働いていた留別郵便局。旧ソ連軍によって占拠された(三上さん提供)
■ずぶぬれの父、忘れられない夜
―三上さんの父親がソ連軍の上陸を本土に伝えたと聞きました。
「父はソ連軍の上陸を軍隊と本土に伝えなければならないと考えましたが、村で唯一通信設備があった郵便局はソ連に占拠されてしまった。そこで父は30キロ離れた択捉島紗那の郵便局に向かいました。紗那の郵便局は根室の無線局と定時連絡をしていました。父が放牧地で馬に馬具をつけると、ソ連兵が気付いて発砲してきましたが、幸い弾は外れました。紗那の郵便局に着いたのは夜9時ごろだったそうです」
「その後、根室の落石の郵便局と繋がり、『28日午前10時、ソ連軍留別に上陸、郵便局は占拠され…』と電文を打ちました。明け方、自宅で『コツコツ』と窓をたたく音がしたので、開けるとずぶぬれの父がいました。父の帰りを待った長い長い夜は一生忘れられません」
■7人のロシア人と生活
―ソ連軍上陸後の島の様子は。
「上陸から3日ほどが過ぎると、民家の接収が始まりました。軍紀を保つため、牢屋(ろうや)も作られました。兵士の子どもたちも島に住むようになりました。冬が近く、新たな家を建てる暇もないので、日本人の家にロシア人が住むようになりました。12月ごろまでは、ロシア人による土木作業や漁業などの強制労働もありました。ただ働きで給料は出ませんでした」
―三上さんの自宅の状況は。
「旅館を買い取ったわが家は広く、多い時で、3家族、計7人のロシア人と一緒に住みました。全員ウクライナ系でした。ある兵士の奥さんはよくピロシキを振る舞ってくれました。世話好きの私の母や大叔母が夫婦げんかの仲裁まで頼まれるほど、付き合いは進みました。日本人が村の外に行かないよう、ソ連兵が見張っていましたが、ロシア人の子どもと一緒だとフリーパスで出ることができました。私は海軍大尉の息子と仲良くなり、よく山野を歩き回りました」
■ケンカが仲良しのきっかけに
―共同生活で印象に残っていることは。
「ある日、私が飼っていた牛がロシア人に殺されたことがきっかけで、イワンという子どもとケンカになりました。私はベルト、相手はナイフを持っていました。彼に詰め寄ったら、私の手がナイフで傷を負ったんです。私は相手をベルトで殴り、向こうも出血していました。私は牢屋に入れられると思いましたが、イワンの父親が息子がナイフを振り回していたことを重く見て、『子どもは仲良くするように』とたしなめました」
「学校でばったりイワンに会うと、『おまえ、けがは大丈夫か』と駆け寄ってきました。それで仲直りして、私たちは仲良くなりました。釣りざおを持って釣りにも行きました。私の左手の親指の付け根の辺りの2カ所にはイワンにつけられた傷がまだ残っています。相当深く刺さりました。手の甲を表にしても裏にしても見えます。毎日顔を洗う度に、島を思い出すんです」

留別にある日本人墓地跡を2019年8月に訪れた墓参団。新型コロナウイルスの感染拡大とロシアのウクライナ侵攻の影響で、これ以降、北方四島への墓参は途絶えている=8月10日(同行記者団撮影)
■仏壇をプレゼント
―2年間のロシア人との共住生活後、日本人は島から引き揚げました。
「引き揚げが命じられたのは47年の夏。引き揚げ船の到着まで10日ばかりありました。干飯をつくり、塩と袋に詰めて救急食にしました。寝具と少しの着替え以外は持ち出すことを許されず、持ち物は知り合いのロシア人にプレゼントしました。家の仏壇は一緒に住んでいたソ連兵の奥さんがほしいと言ったので、あげました。その奥さんは『私たちは本当はこれなの』と言って、ロシア正教会のイコン(肖像画)を母に見せました。ソ連で弾圧されていた正教徒だったんです。秘密を打ち明けるほど、われわれは打ち解けていました」
―引き揚げ時の様子は。
「引き揚げ船の甲板に私たちは群がるように立っていました。見送りのロシア人が闇の中で燃やすたき火だけが、陸の目印でした。私は涙でたき火が大きくなったり、小さくなったりしました。もう島を見るのはこれが最後だと思いましたね。大叔父は『これが千島の見納めか』と言うと、父は『何もないところから漁場や旅館を築くことができた。生きていれば良い夢もある』と話していたのを覚えています」
■「浦島太郎の気持ち分かった」
―戦後、島を何回訪れましたか。
「北方領土へのビザなし渡航には計6回参加しました。留別を訪れたのは引き揚げから約60年がたった2006年。くしくもその日は59年前に旧ソ連軍が上陸した8月28日でした。昔あった橋桁以外は何も残っておらず、私はその時、浦島太郎の気持ちが分かったような気がしました。何十年も心の中で、故郷を思い描いてきました。目をつむれば村の様子が見えます。それなのに、目の前には砂丘とハマナスがあるだけです。現実は今、自分が見ている変わり果てた姿なのか、目をつむった時に見える村なのか、なんだかもう混乱してしまいました」
■記憶は全てパソコンに記録
―元島民の高齢化が進む中、島での記憶をどのように伝えていきますか。また、領土交渉に期待することは。
「今は北方領土について知っていることを全て伝えようと、パソコンで記録を残しています。千島連盟など、元島民団体に寄贈し、自由に見ていただけるようにしたいと思っています。日ロの領土交渉は厳しい状況が続きますが、まずは元島民が自由に行き来できるようになってほしいです。もう一回、島で日本人が魚釣りをしている姿を目に焼き付けたいです」(聞き手 今井裕紀)

「故郷・留別を忘れた日はない」と語る三上洋一さん=2024年4月30日、相模原市
みかみ・よういち 1937年、択捉島留別村生まれ。45年8月の旧ソ連侵攻後、ロシア人と混住を経験。47年に函館に引き揚げた。北大農学部卒で、63年に日本専売公社(現日本たばこ産業)入社。2009~17年まで千島歯舞諸島居住者連盟関東支部副支部長。北方領土の記憶を伝える「語り部」としても活動。87歳。