
北方領土の元島民らが故郷の島を訪問するとともにロシア人の島民を受け入れる「ビザなし交流」の開始から22日で30年となります。ビザなし交流は3月、ウクライナへの軍事侵攻に対する日本の制裁措置に反発してロシアが一方的に停止を表明していて、領土問題の解決に向けて続けられてきた交流がいつ再開できるのか懸念が広がっています。(NHK 2022/4/22)
ビザなし交流は日本人と北方四島に住むロシア人がビザの発給を受けずに相互訪問する枠組みで、30年前の1992年4月22日、ロシア人の第1陣を乗せた船が根室市の花咲港に入港しました。

住民どうしが理解を深めることで領土問題の解決につなげるのがねらいで、これまでに元島民やその子や孫、それに研究者など日本側からおよそ1万4000人、ロシア側からおよそ1万人が参加し、ホームステイなど草の根の交流を重ねてきました。
しかしロシアは3月、ウクライナへの軍事侵攻に対する日本の制裁措置に反発して平和条約交渉を中断し、ビザなし交流などの交流事業も停止すると一方的に発表しました。
交流事業は新型コロナウイルスの感染拡大の影響でおととしから2年連続で中止され、さらにロシア側の停止表明で再開の見通しは立たなくなっています。
元島民の平均年齢は86歳を超えて高齢化が進んでいて、領土問題の解決に向けて30年間続けられてきた交流がいつ再開できるのか、そして再び故郷を訪問できるのか懸念が広がっています。

30年前 1回目のビザなし交流に参加した男性は
根室市に住む得能宏さんは(88)は30年前(1992年5月)、日本側からの1回目のビザなし交流に参加しました。
当時、故郷の北方領土の色丹島では100人近い島に住むロシア人の子どもたちが日本とロシアの国旗を持ち、港で出迎えてくれたといいます。
得能さんは「ふるさとに帰ってきたんだという実感を味わえて感激した。来てよかったと思ったし、こういう訪問がずっと続けばいいなと思った」と振り返りました。
10歳で終戦を迎えた得能さんは、終戦直後の昭和20年9月に旧ソビエト軍が島に上陸したあと、占領下でしばらく暮らし、3年後、13歳のときに島から強制的に退去させられました。

得能さんは領土問題の解決につながればとこれまで30回以上交流事業に参加し、多くのロシア人島民と友好を深めてきました。
中でも、色丹島に住むロシア人男性の1人とは互いに「親子」と呼び合うほどの間柄となり、男性の働きかけで立ち入りが制限された区域にある生家の跡地を訪れることができたといいます。島にある得能家の墓もロシア人の男性やその友人たちが丁寧に掃除してくれていて、新型コロナウイルスの感染拡大の影響で交流事業が中止されたあともオンラインで連絡を取り合いました。得能さんは、こうした草の根の交流が領土問題の解決には欠かせないとして、時機がくればビザなし交流が再開されることを願っています。
得能さんは「島に行ったり来たりする中で、根っこには領土問題があるんだと思い出させるのは大事なことだ。ビザなし交流はロシアに何を言われても続けなければいけないと思う。これで打ち切りになったら、この77年がむだになってしまう。国どうしの交渉だけではダメで時間がかかっても復活させてほしい」と話しています。

ウクライナの現状にみずからの体験重ねる元島民の男性も
標津町に住む福沢英雄さん(81)は歯舞群島・多楽島出身で、コンブ漁を営む両親のもとで暮らしていました。その平穏な生活は、終戦直後の1945年9月上旬、旧ソビエト軍が島に上陸したことで一変しました。
当時5歳だった福沢さんは、銃を持った兵士が家を回って略奪をする様子をいまも鮮明に覚えています。福沢さんは「いきなり土足で上がってきて引き出しやタンスをあけて腕時計や万年筆といった大事な物をあさっていた。鉄砲を向けてわめきちらす兵士もいて、生きるか死ぬかの境地にさらされたことは一生忘れられない」と当時を振り返ります。
福沢さん一家は先祖から受け継いできた家や土地を残して命からがら、船で島から避難しました。それだけに、いまウクライナの子どもたちを伝えるニュースを見ると当時の自分のことを思い出していたたまれない気持ちになるといいます。
福沢さんは「小さい子どもが『死にたくない』と大粒の涙を流して泣きわめいている姿は5歳のときの自分と重ね合わさざるを得ず、胸が張り裂けそうだ。このあとどう暮らしていくのか落ち着かず、心が裂けるような思いをしているのではないか」と思いを寄せています。
つらい思いをした福沢さんですが、ロシアとの交流が領土問題の解決につながればという一心で、ビザなし交流などに16回にわたって参加し、北方領土のすべての島を訪れました。

また、ロシア人の島民をホームステイなどで受け入れ、交流を重ねるうちに親しみがわくようになり、自宅の離れに「北方領土友好館」という看板をかけて交流の写真や記念品を展示しています。
それだけに、ビザなし交流が停止され、これまで縮めてきたロシア人島民との距離がまた広がってしまうことにむなしさを感じています。
福沢さんは「最初はロシア人のことを憎んでいたが交流を続けるうちに性格や考え方を理解できるようになってきた。今までの交流が水の泡になってしまう、振り出しに戻ると思うと悔しくて残念でならない」と話していました。
この30年のうちに20代の参加者も
そのうえで「長い間積み重ねてきた返還運動なので、諦めるわけにはいかない。ロシア側から『もう日本は北方領土を諦めた』と思われたら悔しいので、運動は末代まで続けていかなければいけない」と述べ、ビザなし交流の再開や返還運動の継続に強い意志を示しています。
この30年で、ビザなし交流には、将来の返還運動を担う若い世代も参加するようになっています。
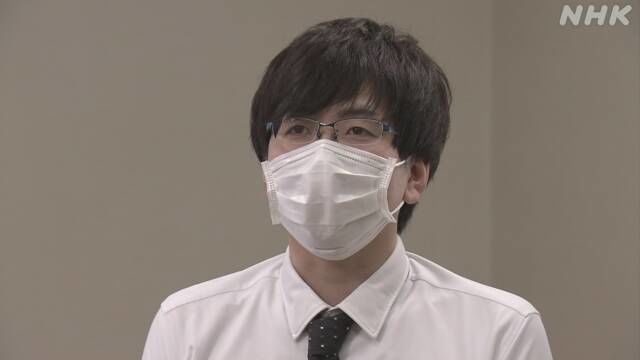
羅臼町の職員、平藤亮さん(28)は祖父が歯舞群島の志発島出身の元島民3世で、ビザなし交流が始まった当時は生まれていなかった世代です。
平藤さんは3年前、ビザなし交流に初めて参加して色丹島を訪問し、ロシア人島民と友好を深めました。
一方、島でロシア人が生活を定着させている現実を目の当たりにし、さらに、返還運動の中心を担ってきた元島民が次第に減っていく中、ビザなし交流を着実に返還に結び付けていく必要性を感じています。
平藤さんは「交流をやめてしまうと、日本はもうそこに力を入れていないんだとロシア側に思われるおそれがあり、続けていくことには意義がある」と話しています。
そのうえで「ビザなし交流が返還につながるという手応えをあまり感じられなかったので、そこにアプローチできるような対話や交流の形を考えていったほうがいいと思う」と話しています。

専門家「何とか“根っこ”を絶やさないように」
ビザなし交流に通訳や研究者として参加してきた岩手県立大学の黒岩幸子特命教授は「ビザなし交流は領土問題の解決と北方領土の返還がゴールで、ゴールは達成されていないものの、この30年間続いたことにとても意味がある。領土問題が長引いているところで、住民どうしがお互いに家にいって泊まりあったりとか仲よくしたりするのは普通はないケースだ」と指摘しています。
そのうえで「ウクライナで戦争が始まっているが、大抵の場合、住民どうしの対立からどんどん火種が大きくなっていく。領土の係争地でありながら、住民どうしの信頼関係ができたというのは世界に誇れることだと思う」と意義を強調しました。
そして、今後のビザなし交流について「ウクライナの戦争が終わることが前提だが、終わった時点で交流を始めるべきで、何とか根っこを絶やさないようにして、いつか交渉再開の時の支えになるような環境づくりをしてほしい」としています。